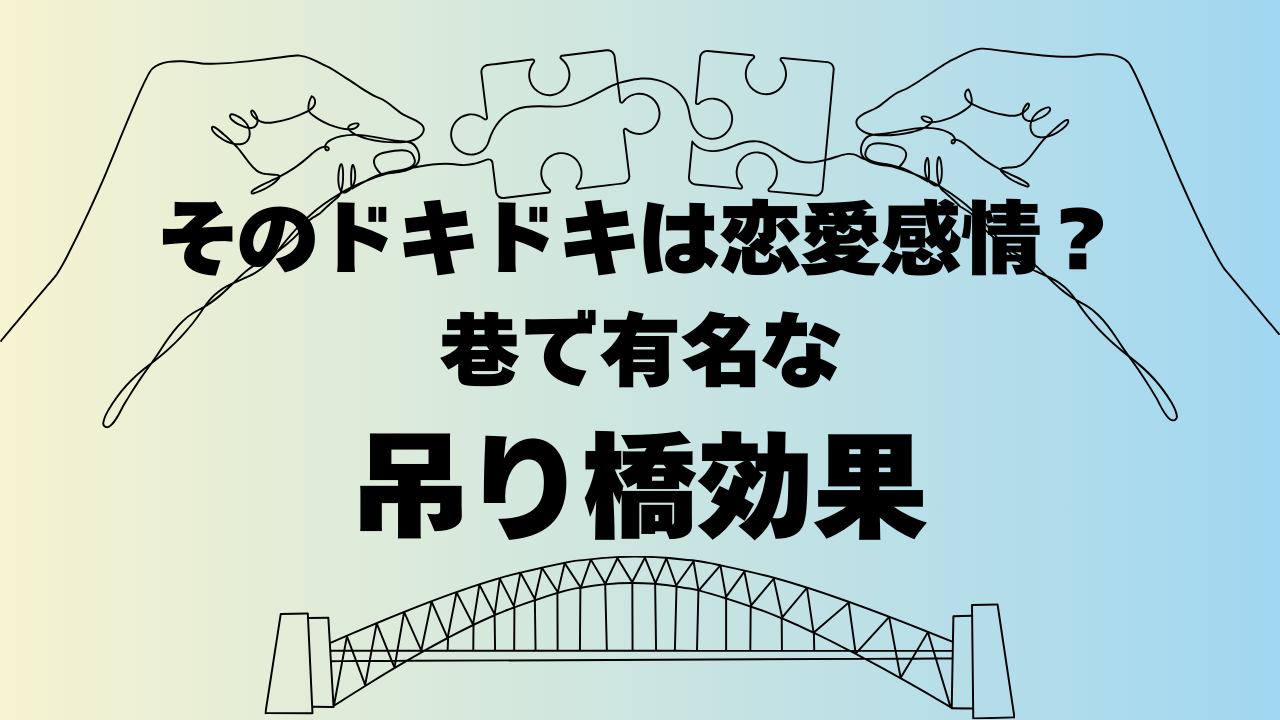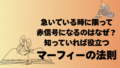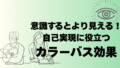吊り橋効果はよく耳にする言葉ではないでしょうか?イメージとしては緊張感や心配の「ドキドキ」を恋愛感情の「ドキドキ」と勘違いしてしまう、と理解されている方が多いと思います。今回はこの吊り橋効果についてさらに理解を深めてみましょう。
吊り橋効果の概要と実験内容
概要
吊り橋効果とは、カナダの心理学者であるダットンとアロンによって1974年に発表された「生理・認知説の吊り橋実験」で実証された感情の生起に関する学説です。吊り橋効果、恋の吊り橋理論とも呼ばれています。 この実験の結果を簡潔にまとめると「吊り橋の上で出会った男女は、普通の場所で出会った男女よりも恋愛感情を抱きやすかった」ということになりますが、感情にも焦点を当てながら補足して説明します。
一般に感情は「出来事→その出来事への解釈→感情」という経路で発生すると考えられています。恋愛で言えば「魅力的な人物に出会う→この人は運命の人かも知れないと解釈する→高揚する・ドキドキする」という経路です。一方、心理学者のスタンレー・シャクターは、実際には「出来事→感情→その感情への解釈」という流れで、感情が認知に先立つ経路もあると考え、情動二要因論という情動の認知説を唱えました。情動二要因論を恋愛で言えば「魅力的な人物に出会う→高揚する・ドキドキする→これは恋(運命の人)?」という流れになります。
このことを証明しようと下記のような実験が行われました。
実験内容

社会心理学者のドナルド・ダットンとアーサー・アロンは、感情が認知より先に生じるのなら、間違った認知に誘導できる可能性があると考えて「恋の吊り橋実験」を行いました。 実験は、18歳から35歳までの独身男性を集め、高さ70メートルの吊り橋と、揺れない橋の2か所で行われました。男性にはそれぞれ橋を渡ってもらいますが、橋の中央で若い女性から突然アンケートを求め話しかけられます。その際「結果に関心があるなら後日電話を下さい」と女性の電話番号を教えています。結果、吊り橋の方の男性18人中9人が電話をかけてきたのに対し、揺れない橋の実験では16人中2人しか電話をかけてきませんでした。この実験により、揺れる橋を渡ることで生じた緊張感がその女性への恋愛感情と誤認され、結果として電話がかかってきやすくなったと推論されました。
なかなか面白い実験ですよね。確かにハラハラ、ドキドキするような状況を一緒に切り抜けた男女が恋に落ちるシーンなどは漫画や映画でもよく描かれます。ただし、この実験には続きがあります。
メリーランド大学のグレゴリー・ホワイトは、吊り橋の緊張感を恋愛感情と誤認するには、実験で声をかける女性が美人かどうか(その女性の魅力度)で結果が左右されるのではと考えました。実際にメイクで魅力を低下させた女性で同様の実験を行ったところ、美人ではない場合では吊り橋効果は逆効果であることがわかっています。
・・・少し言葉に詰まる結果にはなりました。結局、個人(人の魅力)に依存する部分はあることはもちろんだと思いますが、「感情」の発生について解き明かそうとしたこの実験自体は価値があったように思います。
吊り橋効果の活用例と注意点
活用例
吊り橋効果はやはり恋愛で活用されることがほとんどです。いくつか活用例をみてみましょう。
・一緒にジェットコースターに乗ったりやサスペンス映画をみる(緊張感を活用する)
・初対面の際に相手のことや服装などを褒める(初対面の緊張感を活用する)
・一緒に行ったことのない場所に行く、やったことないことをやる(初めての高揚感を活用する)
・一緒にスポーツやゲームなどに参加する(勝敗を分ける緊張感を活用する) など
緊張感や高揚感を共有する、創出することで相手に対する心理的距離が縮まる可能性があります。また最後のスポーツやゲームなどの勝敗が決する競技などは、友人同士でも仲が深まる要因となるでしょう。
注意点
ここまで記事を読んでいただいて申し訳ない気持ちもありますが、吊り橋効果を過信しないことが大切です。実験の最後にもありましたが、対象者の魅力によって結果は変わります。したがって、吊り橋効果は一種の学説として捉え、自分自身の魅力を磨いていくことの方が大切だと思います。
最後に
今回の記事では有名な「吊り橋効果」について触れました。注意点に書いたことがこの記事の結論になるかもしれませんが、感情に対する解釈という考え方は興味深いものでした。また具体例にあるように、心理的距離を近づけていく手段は有効活用できる部分もあると思うので、知識の一つとして覚えておくのはいかがでしょうか。